香川県高松市で開催された芸術士活動視察会に参加して

みなさんこんにちは。 事務局長の坂根ここのです。
福知山芸術文化振興会では、公演やワークショップに研修として参加し、そこで得た知識や経験を福知山での文化活動に活用する仕組みを設けています。
2025年6月18日(水)、香川県で開催された「芸術士活動視察会」に参加しました。
主催は、芸術士の活動を広げている NPO法人アーキペラゴ。
芸術士活動15周年を記念した書籍『可能性の育み 芸術士 アーティストと子どもたち15年の歩み』の出版イベントに合わせて企画されたものです。
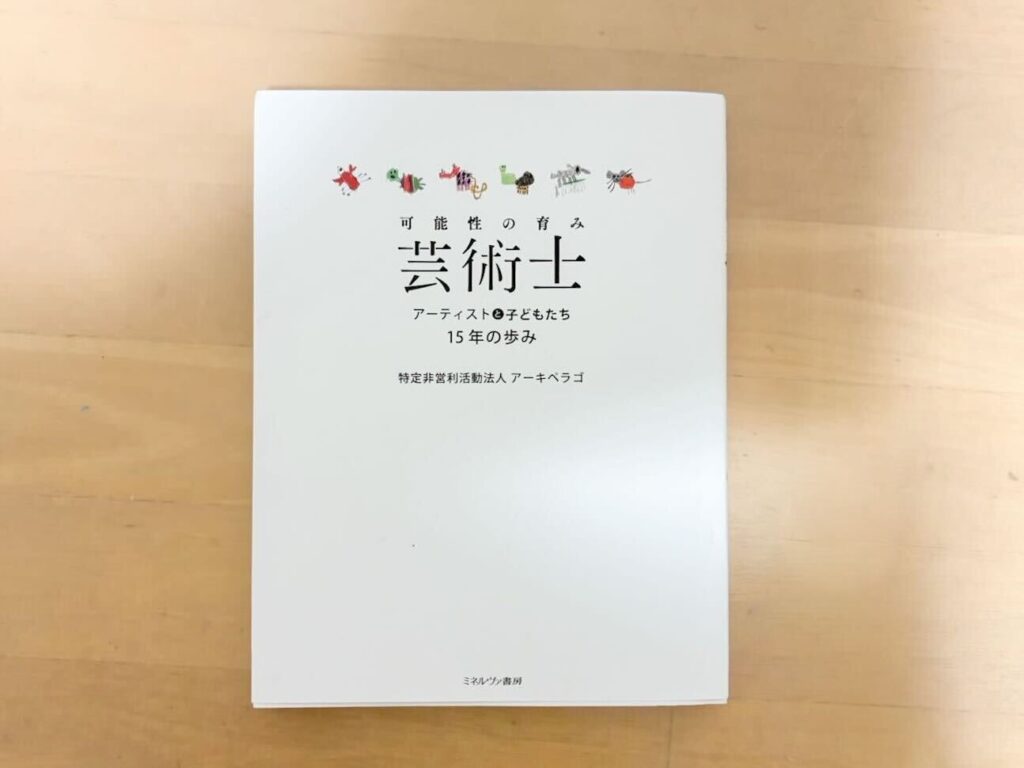
芸術士とは
「芸術士」とは、アーティストとして保育施設に派遣され、子どもたち一人ひとりの価値観や可能性を尊重しながら、表現活動を共に楽しむ専門家のことです。
イタリアのレッジョ・エミリア市で行われている幼児教育アプローチに着想を得て始まり、アーキペラゴが行政や自治体から委託を受けて運営しています。行政・芸術士・保育者の三者が連携して子どもたちの発想を見守り、豊かな保育環境をつくる全国初の取り組みです。
公開視察
午前はカナン十河こども園を訪問し、芸術士の活動を見学しました。この日は、芸術士として勤務する長野由美さんが4歳児クラスで「色水あそび」と「光あそび」を実践されていました。

子どもたちは自分で粉の色やラメを選び、ボトルに入れます。すると、大人が何も言わずとも、子どもたちから自然に「おみずいれてみたい!」という声が。すかさず、長野さんは「いいよ!入れてみたら?」とだけ声をかけました。
自分で量を調節しながら水を入れる子どもたち。「こうやって入れるのよ、量はこれくらい…」などという声かけは一切されず、ずっと見守る長野さんでした。
そして、水の入れ方を工夫している1人の子どもの姿を園長先生とクラス担任の先生が見守りながら「あの子、工夫してるね。成長したね」と気づきを共有されている姿も印象的でした。
色水あそびが盛り上がり始めた頃、長野さんは懐中電灯を持ち出しました。これは、前週に隣の年長クラスで使っていたもので、ひとつ下の4歳児さんにとっては憧れの道具でした。
懐中電灯が配られると、下から照らしてみたり友だちの色水と一緒に照らしてみたり、どんどん工夫して遊ぶ姿が見られました。次第に絵本やおもちゃに光を当てるなど、発想を広げながら遊びを展開していく子どもたちでした。
活動が終わると、職員室に戻り、視察に来られていた大学教授の喜代美先生と、園長先生との反省会です。声かけをした場面、しなかった場面など、長野さんの意図を聞き取っていき、1時間の活動を細かく振り返っておられました。
今回の長野さんの活動では、通常の保育現場では準備が難しいような専門的な画材が導入されていました。また、芸術士が活動進行を担うことで、担任の先生が子ども一人ひとりに丁寧に関わることができている姿がありました。
また、担任が客観的にクラス全体を観察できることで、1人では気づくことのできない子どもの小さな変化に気づくことができ、園内での共有や振り返りにもつながっている点が印象に残りました。
出版記念イベントの聴講

午後はサンポートホール高松で、出版記念イベントを聴講しました。
プログラムは下記の通り。
1.学習院大学教授・秋田喜代美先生による「芸術士の活動をレッジョ・エミリア教育の視点から考える」講演
2.秋田先生と園長先生、長野さんによるリレートーク
講演とリレートークを通して、芸術士の実践が子どもたちの発達や、保育者の芸術的感性の成長にとても大きな意味をもつことを学びました。
さらに、一人ひとりが思いをもって芸術士活動に関わっておられること、そして現場の保育者や管理職、大学の専門家など、さまざまな人の理解と前向きな思いによってこの活動が支えられていることも、深く感じ取ることができました。
今後に活かしたいこと
アートの専門家が保育に入ることで、子どもたちの感性や創造性が豊かに育まれ、しなやかな心や体を育てることができるだけでなく、保育者自身も新しい視点やヒントを得ることができます。
そして、専門家に活動を任せる時間があるからこそ、保育者は子どもたちとじっくり向き合うことができるのだと実感しました。
今回学んだことを踏まえ、自分の音楽療育や保育の経験を重ねながら、地域における芸術文化的な支援や協働の可能性を見出し、伝えていくという役割を担えるようになりたいと思いました。
今回学んだことを今後の活動につなげていきたいと思います。





